どうも、就労系福祉サービスの管理者兼サービス管理責任者を8年以上しているナッツです。
障害や病気を抱えながらも自分に合った働き方をしたい人の収入アップ、スキルアップを応援したいと思い、情報を発信しています。
年金の受給を考えている方の中には、「働きながらでも受給できるの?」「申請って難しいのか?」と不安や疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
就労移行支援の利用者さんからもよく相談を受ける内容です。
本記事では、障害年金を受給するための条件やもらえる金額、申請のポイントなど、初心者が知りたい情報を分かりやすく解説します。
知らなかったがためにもらえるはずだったお金を取りこぼすことがないよう、ライフハックとして身につけておきましょう。
最初に結論として、働きながらでも障害年金をもらうことは可能です。
ただし、障害年金は障害の程度に応じて支給されるというルールがあり、ケースによってはフルタイム就労できる=障害の程度が軽いと判断され、支給が停止される可能性もあります。
障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障をきたした場合にもらえる公的年金制度の一つです。
公的年金制度には、他に65歳からもらえる老齢年金、夫が亡くなった時にもらえる寡婦年金があります。
障害年金は大きく分けて2種類あり、国民年金の「障害基礎年金」と厚生年金の「障害厚生年金」があります。
障害の程度に基づいて支給されるため、就労の有無や年収は直接、影響しません。
ただし、働き方や収入によっては「障害の程度が軽減された」と判断され、支給を停止される可能性もあります。

それぞれの概要は以下のとおりです。
条件を満たすパートとは(タップして開く)
以下の条件全てを満たす者です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が原則1年以上見込まれる
- 月額賃金が8.8万円(年収約106万円)以上
- 従業員501人以上の企業
- 学生でないこと
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
| 等級範囲 | 1~2級 | 1~3級 |
| 加入者 (対象は?) | ・第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職など) ・第2号被保険者(会社員・条件を満たすパート、公務員、私立学校教職員など) ・第3号被保険者(第2号被保険者の扶養配偶者) ※全国民に加入義務があり、20歳になったら自動的に加入 | 第2号被保険者(会社員・条件を満たすパート、公務員、私立学校教職員など)※強制加入 |
| 年齢 (何歳から?) | 加入年齢 20歳~ 支給開始 最短20歳~ | 加入年齢・支給開始ともに人による |
| 金額 (いくら?) | 定額 | 加入期間や給与によって変動 |
| 申請窓口 (どこで?) | 区市町村 | 年金事務所(基礎年金と同時なら区市町村も可) |
1級(日常生活が一人ではほぼ不可能)
基準:介助なしでは日常生活がほぼ不可能。働いている人はごくわずか。
- 身体障害:両手両足の麻痺
- 精神障害:自傷行為や幻覚が常時あり長期入院
- 知的障害:重度(IQ35以下)で常時支援が必要
2級(日常生活に著しい制限)
基準:日常生活に必ずしも助けは必要ない。労働が極端に制限される状態(短時間・軽作業以外困難など)。
- 身体障害:脊髄損傷による車いす生活
- 精神障害:発達障害で対人関係困難、短時間勤務であれば可能
- 知的障害:簡単な会話は可、身の回りのことは支援があれば自立。中度(IQ35~50程度)
3級(労働に相当の制限) ※厚生年金のみ
基準:傷病が治っておらず、労働に制限がある状態。負荷次第ではフルタイム就労が可能な場合も。
- 身体障害:片腕欠損
- 精神障害:うつ病、パート、週30時間可
- 知的障害:軽度(IQ50~70程度)
日常会話可、単純作業ならフルタイム可能だが、複雑な仕事や対人対応に制限。
受給要件
受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に基礎年金、または厚生年金に加入(←重要)していること。(厚生年金加入者は自動的に基礎年金にも加入) - 保険料納付要件
初診日の前日において次のいずれかであること。
・加入期間の3分の2以上の保険料を納めている(免除・猶予期間含む)
・直近1年間に保険料の未納がない
例:30歳の誕生日を迎えた次の日に初診
20〜30歳の10年間(120ヶ月)で6年8ヶ月(80ヶ月)以上払っている➡OK
29~30歳の一年間だけ未納せず払った➡OK
20~30歳(29~30歳の直近1年間未納)で6年8ヶ月(80ヶ月)未満➡アウト
障害状態要件
初診日から1年6ヶ月後の障害認定日において、障害等級1級、または2級(厚生年金の場合は3級も対象)に該当すること。
事故等で失明や切断など即時状態が固定と判断できる場合は1年6ヶ月後を待たず認定も。
障害年金に関係する年齢
加入年齢=支給年齢ではないことに注意!
受給要件にもありますが、加入できる年齢がきたらすぐに受給できるわけではありません。
四肢切断、失明などのようにすぐに障害が固定されたと判断できるものを除いて1年6ヶ月待機
➡そこから申請して1~3ヶ月程度審査
➡決定して初回の支給まで1~2ヶ月かかります。
基礎年金 19歳で初診➡20歳6ヶ月で認定➡申請➡支給
【即時固定の場合】19歳で認定➡20歳で支給開始可能
厚生年金 18歳2ヶ月で初診➡19歳8ヶ月で認定➡申請➡支給
【即時固定の場合】18歳2ヶ月で認定➡申請➡支給
※厳密には多少ずれが生じますが、ここではわかりやすくシンプルにしています。
お金に余裕がない人・家庭は待機期間中に貯金が底をついたり、失業保険が切れることも考えられるため、なるべく早めに病院を受診しましょう。
基礎年金と厚生年金はルールが違うため、状況によって受け取れる年金にも違いがでてきます。

初診日となる年齢は何歳から?
障害基礎年金
①基礎年金加入中の20歳~60歳、または任意加入期間中の60歳~65歳未満
②先天性(生まれた時から)の障害:出生日(あとからわかった場合は初診日とされることも)
20歳前に負った障害(事故や病気など)
※②は特例として、保険料納付要件が免除されます
※任意加入期間中とは、老齢基礎年金の受給資格(10年以上)を満たす、あるいは、受け取る年金を増やすために、任意で加入できる期間のことです
障害厚生年金
厚生年金加入中であれば年齢に制限はありません。
| 基礎年金 | 厚生年金 | ポイント | |
| 加入年齢 | 20歳~ | 人による | 厚生年金は子役俳優が加入することも。 |
| 支給開始 | 最短20歳~ | 人による | 条件によっては、厚生年金の方が先にもらえる |
| 初診日 | ①加入中の20歳~60歳、または任意加入期間中の60歳~65歳未満 ②先天性(生まれた時から)の障害、20歳前に負った障害(事故、病気など) | 加入中であれば年齢に制限なし | 年金加入中であることがポイント 基礎年金の②は特例 |
金額はいくらもらえる?
障害年金の支給パターンは、障害基礎年金単独、障害厚生年金単独、両方の3つです。
障害等級は基礎年金が1級なら厚生年金も1級となり、等級は同じになります。
障害基礎年金
自営業や学生、無職などの方は基礎年金だけとなることが多いです。
金額は納付期間に関係なく、固定額が支給されます。
2024年度基準で金額は以下の通りです。
- 1級: 年額約102万円(月約8.5万円)
- 2級: 年額約81.6万円(月約6.8万円)
金額は物価や賃金の変動次第で若干変わる可能性があります。
最新情報は日本年金機構の公式サイトで確認できます。
障害厚生年金
1・2級の場合、基礎年金との併給になりますが、
審査の結果、3級となった場合、基礎年金には3級がないため、厚生年金のみの受給となります。
金額は加入期間や報酬(給与)に応じて変動します。
受給金額 = 平均標準報酬額×加入月数×0.005481(係数)
※1級の場合、1.25倍
3級の場合、59.6万円(最低保障額)より低いと最低保障額が適用されます。
わかりやすいように月収30万円と20万円の2つの例をみてみましょう。
例1:会社員(第2号被保険者)、平均月収30万円、加入10年
30万円×120ヶ月×0.005481=約19.7万円
1級なら基礎年金年額約102万円+(厚生年金約19.7万円×1.25)=約136.6万円
2級なら基礎年金年額約81.6万円+厚生年金約19.7万円=約101.3万円
3級なら最低保障額以下のため59.6万円に調整
| 等級 | 基礎年金(単独) | 厚生年金(単独) | 基礎+厚生(併給) |
| 1級 | 102万円 | 約19.7万円×1.25 | 約136.6万円 |
| 2級 | 81.6万円 | 約19.7万円 | 約101.3万円 |
| 3級 | 対象外 | 最低保障額以下のため59.6万円 | 基礎年金対象外のため59.6万円 |
例2:会社員(第2号被保険者)、平均月収20万円、加入1年
20万円×12ヶ月×0.005481=約1.3万円 ⇒ 3級なら最低保障額の59.6万円に調整。
加算
障害年金には「子の加算」と「配偶者加算」の2つの加算があります。
子の加算は基礎年金、厚生年金共通の加算ですが、配偶者加算は厚生年金のみとなります。
| 加算 | 基礎年金 | 厚生年金 | 金額 |
| 子の加算 | ○ | ○ | 年間約23.4万円(月額約1.9万) ※子3人目以降は年間約7.8万円 |
| 配偶者加算 | × | ○ | 年間約23.4万円(月額約1.9万) |
子の加算
生計をともにする18歳未満(障害等級1・2級の子であれば20歳未満)一人につき年間約23.4万円(月額約1.9万)支給されます。 ※子3人目以降は年間約7.8万円
配偶者加算
金額は子の加算と同じ年間約23.4万円(月額約1.9万)です。
支給要件は、配偶者が65歳未満で、生計を共にしていることです。
所得制限があり、配偶者自身の前年所得が約462万円を超えると停止となります。
遡及
遡及とは、期日を遡って請求することをいいます。
遡及が認められた場合、申請していれば過去にもらえるはずだったお金をまとめて受給することができます。
遡及できる期間は最大5年間です。
遡及の主なケースには下記があります。
- 障害年金の存在を知らず、後から申請した
- 自分は障害年金に該当しないと思っていた
- 書類の不備で手続きが遅れた
- 他のことで忙しく、手続きどころではなかった
「❶障害年金の存在を知らず、後から申請した」を事例として考えてみましょう。
25歳で受診(初診日)。30歳で障害年金の存在を知り、医師に相談。
➡障害認定日が26歳6ヶ月なら3年6ヶ月分遡及可能
【20歳前障害の場合】
例:19歳で初診。20歳6ヶ月で障害年金の存在を知り、医師に相談
➡20歳前障害特例により、20歳まで遡及可能(通常の場合、20歳6ヶ月)
20歳前障害は❷~❹のケースでも当てはまります。
ただし、「❸書類の不備で手続きが遅れた」は遅れたといっても障害認定日から何年も遅れることは考えにくいため、遡及は数ヶ月に収まると考えられます。
※これらはルール上可能ですが、実際のケースは人によって様々なため、受給を保証するものではないことにご留意ください。
その他は数年単位で遡及が発生することが考えられますが、遡及できるのは最大5年間のため、仮に事例の初診日が21歳だった場合、受け取れるはずだった1年6ヶ月分は時効として失われます。
私が就労移行で支援していた利用者さんのケースも❶にあたりますが、無事遡及が認められ、百万単位のお金を受給することができました。
手続きの流れ
手続きの際に必要な主な書類は以下の通りです。
- ステップ1
- ステップ2
- ステップ3
- ステップ4
- ステップ5
ステップ1 初診日を確認する
まず、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)を特定します。
初診日を確認する書類として、初診日の病院のカルテ、領収書、診察券などがあります。
できればカルテが望ましいですが、廃院や受診が古すぎてカルテがないという場合もありえます。
そんな場合には、領収書や診察券が残っていないか探してみましょう。
ステップ2 保険料納付状況をチェック
次に、初診日前の基礎年金、厚生年金の納付状況を確認します。
受給要件でも挙げたとおり、初診日の前日時点で「加入期間の3分の2以上納付」、または「直近1年間未納なし」となっていることが必要です。
納付状況の確認方法として、年金事務所やねんきんネットで年金記録を照会する方法があります。
特にねんきんネットは「基礎年金番号」がわかればオンラインで確認(5分程度)することができるため、まずはねんきんネットで確認するのがおすすめです。
「基礎年金番号」は年金手帳や基礎年金番号通知書に記載されています。
年金手帳を紛失してしまった時の再発行手順
- 最寄りの年金事務所、もしくは市区町村窓口へ行く(電話で予約しておくとスムーズ)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参 - 「年金手帳再交付申請書」を記入
基礎年金番号がわかれば記入、わからない場合は職員が照会してくれます。 - 約1〜2ヶ月で自宅に新しい年金手帳が届く(再発行は無料)
年金手帳は会社で求められる場合もあるため、大切に保管しておきましょう。
ねんきんネットを使ったことがないという方は下記も参考にしてください。
ねんきんネット初回登録手順(10分程度)
- 日本年金機構の「ねんきんネット」にアクセス
- 「利用登録」をクリック
基礎年金番号とメールアドレスでID・パスワードを作成(5〜10分で完了) - ログイン後、「年金記録の確認」を選択。納付済み月数、未納期間、厚生年金加入歴が画面に表示
- 必要に応じてPDFでダウンロード、もしくは印刷
納付状況は「ねんきん定期便」でも確認できますが、最新情報は年金事務所かねんきんネットで確認が確実です。
ねんきん定期便とは、年金制度を運営・管理する日本年金機構が毎年、誕生月に送ってくるハガキや封書で、あなたの年金加入記録や将来の見込み額が載っています。
会社員は年金保険料が給与から天引きされるため納付漏れの心配はありませんが、自営業や失業中で長い間納付を忘れていたという場合は、要件に当てはまらない可能性が高くなります。
この際、免除or猶予申請をしていれば「納付済み」扱いとなるため、記憶を確認してみましょう。
ステップ3 医師に診断書を依頼
障害認定日(初診日+1年6ヶ月後)の状態を証明するため、主治医に診断書を作成してもらいます。
これは初診時と病院が違う場合でも大丈夫です。
診断書作成費用は病院にもよりますが、5,000円~15,000円程度が相場です。
受給には審査があるため、「日常生活や労働への影響」を具体的に書いてもらうのが鍵となります。
これには医師との関係性や意向をくんでくれやすいかも関係しているため、話しやすい信頼できる病院選びも重要です。
ステップ4 必要書類をそろえる
主な必要書類にそって書類をそろえます。
書類不備で受理してもらえないと時間のロスにつながります。
手続きには時間がかかるため、経済的事情でなるべく早く受給したいという方は、提出する際、役所や年金事務所に「これで足りますか?」と確認しましょう。
ステップ5 役所・年金事務所に提出
提出先は住んでいる地域の役所、もしくは年金事務所です。
持参、もしくは郵送で送ります。
この際の注意点として、厚生年金だけの申請は、役所では受け取ってもらえない可能性があります。その際は年金事務所に提出しましょう。
審査期間の目安は2〜3ヶ月です。
スムーズにいけば1ヶ月程度で結果が出ることもありますが、書類に不備があったり、年度末は繁忙期のため遅れがちです。
決定通知書が届き、受給が決まったら翌月、もしくは翌々月から支給が始まります。(受給日は偶数月15日払い)
つまり、申請してから支給まで最低でも3ヶ月~5ヶ月はかかるとみておきましょう。
申請方法
申請方法は大きく分けて以下の2つがあります。
このほかに、相談支援事業所などの支援機関にサポートをお願いするという方法もありますが、申請のサポートができる事業所は限定的です。
| 方法 | 費用の目安 | メリット | デメリット |
| 自分・家族が申請 | 診断書代など(5,000〜15,000円程度) | 費用が安く済む | 書類ミスのリスク、負担の重さ |
| 社労士に依頼 | 着手金0〜5万円+成功報酬約10〜30万円ほか | 成功率UP、負担軽減 | 費用がかかる、社労士を選ぶ手間 |
自分で申請する、家族に申請してもらう
- 年金事務所で「年金請求書」や必要書類リストを入手
- 医師に診断書作成を依頼
- 初診日証明(受診状況等証明書)、戸籍謄本、所得証明などを準備
- 書類提出(窓口or郵送)
こちらの方法のメリットはなんといっても費用が診断書代など(5,000〜15,000円程度)に抑えられることです。
ただ、制度の理解に頭を使ったり、年金申請に必要な書類を集めるのは中々にエネルギーが必要です。
書き方がわからず書類の不備で返されたり、書類が足りず何度も足を運ぶことになったり、途中で挫折して結局社労士にお願いして時間をロスすることも…。
決してできないことではありませんが、余裕のある人、調べながら作業するのが苦にならない人、周囲の助けも借りながら進められる人でないと難しいかもしれません。
社労士に依頼する
- 社労士に相談(初回無料なところが多い)
- 契約(着手金の支払いや成功報酬の確認)
- 社労士が書類準備や医師との調整を代行
- 書類提出
こちらのメリットは、専門知識をもったプロに面倒な手続きや資料集めをお任せできること。
ですが、依頼には費用がかかります。
費用は社労士事務所によって変わり、着手金0〜5万円+成功報酬約10〜30万円(2〜3ヶ月分)が必要です。
成功報酬分の支払いは、障害年金から出すことが可能です。
大きな支出となりますが、受給できれば多くの場合損をすることはないため、時間と手間を節約することができます。
利用者さんから相談を受け、社労士を通して申請された方の中には、「社労士さんと話したり、書類を確認するだけでも大変だったのでプロに任せて良かった」という声もありました。
ただ、社労士に依頼したからといって必ず通るわけではないため、障害年金を専門とする事務所や実績豊富な事務所を選びましょう。
免除・猶予
基礎年金には、経済的理由で保険料を払えない人を救済するための免除・猶予制度があります。(基礎年金のみ)
申請すれば、該当期間の保険料が「納付済み」になり、保険料の未納を防げます。
種類は下記の5つがあります。
- 全額免除
- 一部免除(4分の3、半額、4分の1免除)
- 納付猶予(保険料納付を将来に繰り延べ)
- 学生納付特例(学生期間の保険料を猶予)
- 法定免除
具体例を出すと、次のような場合に納付要件がクリアになります。
- 加入15年(180ヶ月)、納付5年+免除7年=12年(144ヶ月)
144÷180=80% > 3分の2(66.6%) ➡ 受給可 - 初診日前の直近1年間が免除・猶予期間なら「納付済み」となり、受給可
申請方法は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を年金事務所、もしくは役所へ提出。
申請期間は年度ごと(7月~翌年6月まで)の1年間が基本です。
未納によって年金受給ができない人が多いため、のちのち後悔しないよう、支払えない場合は手続きしておきましょう。
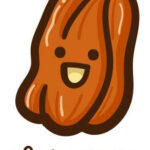
ここが大きな分かれ道になることが多いよ
更新は何年ごと?
障害年金は更新制となっており、申請が通ったらずっと受給できるわけではありません。
障害の状態が変化する可能性がある場合、一定期間ごとに「障害の程度」を確認します。
一部の重度、かつ回復見込みのない障害(例: 両目失明、四肢欠損)は永久認定として、更新不要になることもあります。
更新のタイミングは初回支給決定時に「次回診断書提出年月」が指定されます。
更新期限の約3ヶ月前に日本年金機構から通知(お知らせ)が届くため、主治医に「障害状態確認届(診断書)」を書いてもらい提出します。
提出した診断書をもとに、障害等級(1〜3級)が再判定され、
- 「継続」
- 「変更(等級変更)」
- 「支給停止」
のいずれかが決定されます。
更新期間は1~5年ごとが一般的で、障害内容によって年数は変わります。
- 1年:症状が変動しやすく、改善の可能性が高い場合。
- 2〜3年:中程度の固定性、経過観察が必要な場合。
- 4〜5年:ほぼ固定だが、まれに変化する可能性がある場合。
| 精神障害 | 身体障害 | 知的障害 | |
| 間隔 | 1~3年が多い | 3〜5年または永久認定 | 永久認定が多い |
| 理由 | 症状の回復・悪化の可能性があるため | 障害種類によって変動 | 基本的に回復の見込みが少なく、状態が安定していることが多いため |
| 備考 | 就労状況や日常生活の様子も変わりやすい | 形性疾患や進行性のもの(例:多発性硬化症など)の場合は、数年ごとに確認が必要 | 年齢による発達状況を反映するため、未成年では数年ごとの更新が求められることがあります |
働きながら受給する際の注意点
例えば、現在の就労状況がフルタイム勤務や高収入の場合、主治医の書き方によっては「障害が軽減された」と判断され、支給停止となる可能性があります。
障害状態確認届(診断書)を書いてもらう際には、「なんとか工夫して働けてはいるが障害の状態は変わっていない」ことなどをしっかり伝え、書いてもらうようにしましょう。
障害年金を受給するためのポイント
申請のタイミング
復職、転職、就労移行支援などの支援機関を使って再就職を考えている方は、働き始める前に申請することがおすすめです。
理由は、働けていない現在の状況から医師が年金の必要性を客観的に示しやすいためです。
未納期間を作らない
障害年金を受給するには、初診日の前日時点で保険料納付要件を満たしている必要があり、これが壁になって受給できないケースが少なくありません。
年金は過去2年以内であれば遡って納付(追納)することもできます。
病気や事故はいつ降りかかるかわかりません。
もしもの備えとして、免除・猶予申請をするか、追納をしておきましょう。
Q&A集
審査に落ちたらもう受給できない?
いいえ、できます。
書類の不備を直したり、受給の妥当性を証明できる内容や資料を用意して再申請にのぞみましょう。
更新で打ち切り(支給停止)になったらもう受給できない?
いいえ、できます。
ただし、病気・障害の再発、悪化が受診によって認められ、認定日(1年6ヶ月後)を待ってからの申請となるため、再開するには時間がかかります。
支給停止に納得いかない場合は、3ヶ月以内に不服申し立てを行いましょう。
不服申し立てとは、下された決定を見直してもらう手続きのことです。
具体的には、書類や証拠を再審査したり、追加の資料を提出して再検討を求めます。
障害年金を受給するデメリットはある?
障害年金を受給したら、ほかの人に知られてしまうのではないか、誤解や偏見を受けるんじゃないかと心配になる方もいるかもしれません。
しかし、障害年金を受給してるかどうかは、自分から伝えない限り、会社を含め他の人に知られることはないので安心してください。
最短で受給できる年齢は何歳から?
基礎年金 ➡ 20歳
厚生年金 ➡ 人による
詳しくはこちら。
障害年金から税金は引かれる?
いいえ、課税されません。
年収: 障害年金100万円+給与300万円。
課税所得: 300万円のみ(100万円はカウントされない)
確定申告の際、申告の必要はありません。
蛇足ですが、老齢年金は課税されます。
障害者手帳を持っていないと受給できない?
いいえ、受給できます。
障害者手帳と障害年金は別な制度であるため、手帳を持っていないからといって心配はいりません。
障害年金は何歳までもらえる?
年齢制限はありません。
しかし、1~5年ごとの更新によって、障害が軽くなったと判断された場合、打ち切り(支給停止)となる可能性があります。
その他の障害年金に関係する制度
- 障害手当金
- 障害年金生活者支援給付金
障害手当金
障害手当金は厚生年金の一種です。
3級よりも軽い障害の場合に一時金として支給されます。
金額は給与と加入期間で変わります。
〔平均標準報酬額×加入月数×0.005481(係数)〕× 2年分
※〔〕内が最低保障額の59.6万円以下の場合は59.6万円× 2年分となります。
受給要件は、初診日要件、保険料納付要件は共通で障害状態要件のみ違います。
- 初診日要件
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に厚生年金に加入していること。 - 保険料納付要件
初診日の前日において次のいずれかであること。
・加入期間の3分の2以上の保険料を納めている(免除・猶予期間含む)
・直近1年間に保険料の未納がない - 障害状態要件
初診日から5年以内に治ったものの、3級より軽い障害が残っていること
障害年金生活者支援給付金
障害年金を受給している人のうち、所得が一定以下の場合、毎月の障害年金に上乗せして給付金が支給されます。
金額は
- 1級 6,275円(2級の1.25倍)
- 2級 5,020円
受給要件は以下の通りです。
- 障害基礎年金を受給していること(厚生年金のみの受給者は対象外)
- 前年の所得が一定以下であること(2024年度時点で年間所得が約472万円)
まとめ
障害年金は、働きながらでも受給できる制度ですが、障害の程度や働き方によっては支給停止の可能性もあります。
就労と年金受給のバランスを考えながら、無理のない範囲で働くことが大切です。
また、障害年金の手続きや受給資格について不安がある場合は、年金事務所や専門の社労士に相談するのも一つの方法です。
適切な支援を受けながら、安心して生活できる環境を整えていきましょう。
【あわせて読みたい】

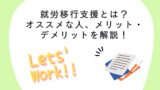


コメント